問題提起
「新規顧客ばかりに目が向き、既存顧客への対応が後回しになっていませんか?」
リテンション施策が軽視されがちな中、優良顧客の流出は大きな機会損失につながります。
その課題を解決するのが、RFM分析という手法です。
この分析を活用すれば、効率的に顧客価値を見極め、最適な施策を打つことが可能になります。
RFM分析の基本とその目的
RFM分析は、顧客の購買行動を「Recency(最終購買日)」「Frequency(購買頻度)」「Monetary(累計購買金額)」の3軸で評価し、顧客をセグメント化するマーケティング手法です。
この手法の目的は、「今、価値の高い顧客」と「放置すると離反するリスクがある顧客」を数値で明確にし、ターゲット別にアプローチすることです。
- Recency(最新性):最後に購入してからどのくらい日が経っているか
- Frequency(頻度):どのくらいの頻度で購入しているか
- Monetary(購入金額):どれだけの金額を消費しているか
それぞれの指標にスコアをつけて、最も価値の高い顧客群からアプローチ優先度を判断します。
RFM分析の進め方と活用法
RFMスコアのつけ方
- 顧客データを集計:購買履歴から、各顧客の「最終購入日」「購入回数」「累計金額」を抽出します。
- スコア化:それぞれの項目に対して、顧客を相対評価し、例えば上位20%を「5」、下位20%を「1」といった形でスコアをつけます。
- セグメント化:RFMの3指標を組み合わせたスコア(例:555や321など)で分類します。
セグメント例と対応施策
- 555(チャンピオン顧客)
購買頻度も金額も高く、最近も購入している優良顧客。
→ロイヤルティプログラムやVIP限定キャンペーンで満足度を維持。 - 155(離反顧客)
金額も頻度も高かったが、最近は購入していない。
→再アプローチメールや限定割引などでカムバックを促進。 - 311(新規・見込み顧客)
最近購入したが、頻度も金額も低い。
→リピート購入を促すクロスセル施策やステップメールが効果的。
運用上のポイント
- 定期的な更新がカギ:週次や月次でスコアを見直し、リアルタイムなアクションが取れる体制が理想です。
- 他のデータとの掛け合わせ:NPSや属性情報と組み合わせることで、より精度の高い施策立案が可能になります。
良い例と悪い例を比較して解説
良い例:D2Cアパレルブランドの場合
例えば、あるD2Cアパレルブランドでは、RFM分析により「Rが高くFとMが中程度」の新興ロイヤル顧客にターゲットを絞って、LINE限定クーポンを配信しました。
結果、対象顧客のLTVが半年で1.5倍に向上し、リテンション率も20%以上改善しました。
悪い例:一律メルマガ配信の通販サイト
逆に、全顧客に一律のキャンペーンメールを送っていたECサイトでは、開封率もクリック率も頭打ちとなり、最終的には配信解除が続出。
「すべての顧客が同じ反応を示すわけではない」という基本が無視された施策は、逆効果になるリスクが高いのです。
まとめ:顧客の見える化でマーケティングを効率化しよう
RFM分析は、データをもとに「どの顧客に、どんなタイミングで、どのような施策をすべきか」を判断できる非常に有効な手段です。
特に中長期的なLTV向上、ロイヤル顧客の育成には欠かせません。
Excelでも十分に実践できるため、まずは自社の顧客データから「見える化」を始めてみてください。
あなたのビジネスでも、RFM分析を取り入れて顧客との関係性を強化しませんか?

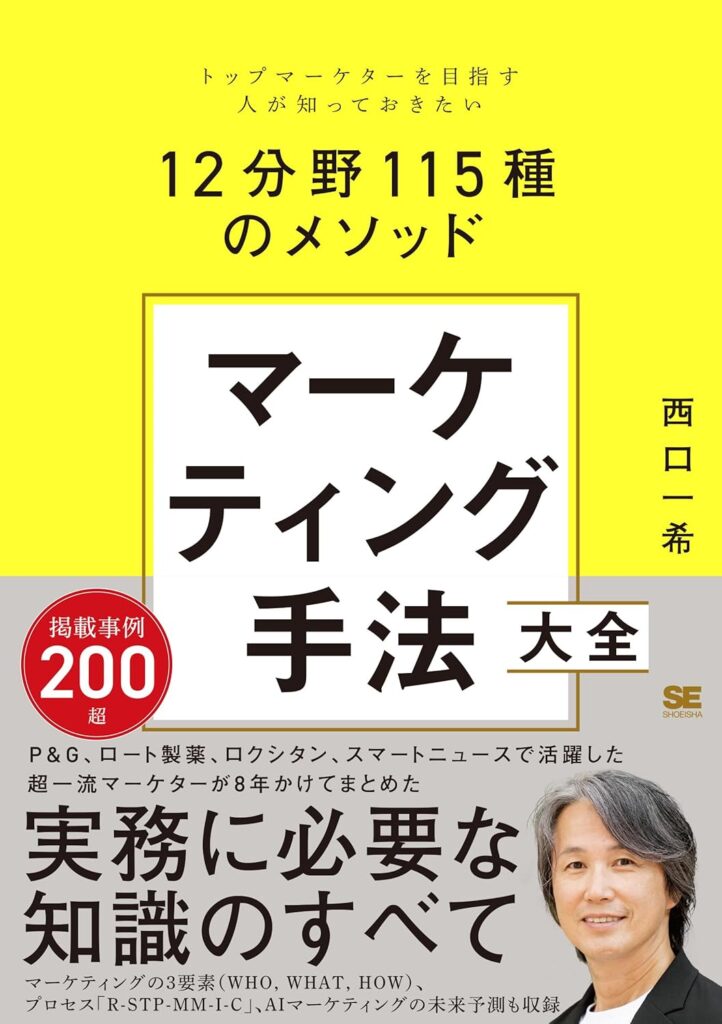 マーケティング手法大全
マーケティング手法大全 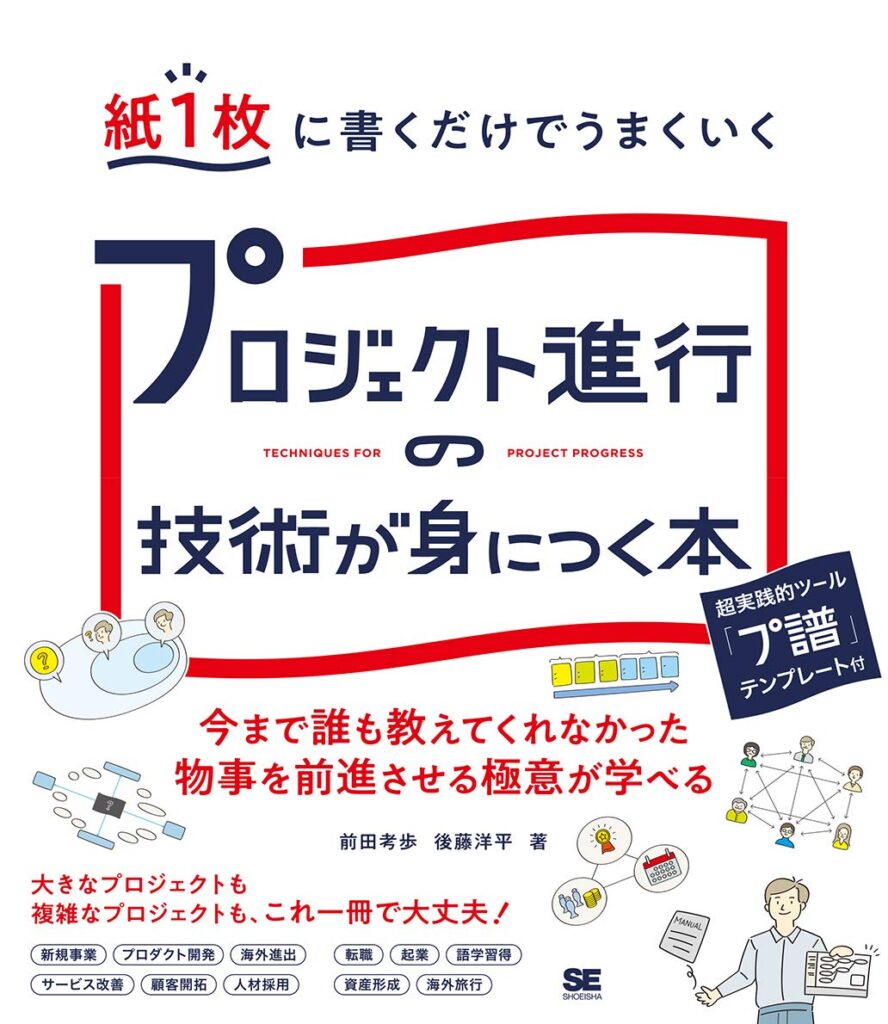 プロジェクト進行の技術が身につく本
プロジェクト進行の技術が身につく本  デザインをつくる イメージをつくる ブランドをつくる
デザインをつくる イメージをつくる ブランドをつくる